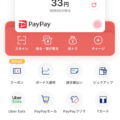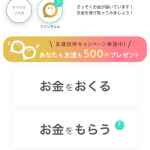QRコード決済とは、スマーフォンでQRコードを読み取ってスマホ上で決済、もしくは画面に表示されたQRコードを読み取ってもらって決済といういずれかの手順で、紐付けられたクレジットカードや事前にチャージした電子マネーなどで支払うこと。キャッシュレス化が進んだ中国のWeChat PayやAliPayがこのQRコード決済です。
このページでは日本でローンチされているQRコード決済サービス、される予定のサービスを一覧でご紹介しているのでぜひ目を通してみてください。まずはこのページの長さをご覧いただければ、日本のQRコード決済(バーコード決済)の現状がなんとなく察して頂けるかと思います。
※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
2017年から現在まで新しいサービスが発表され次第、終了次第、随時更新しています(バーコード決済も同じコード決済という括りで含みます)。
使い続けるかどうかはともかく、まだ使ったことがない方はよく目にするものの中からいずれかをキャンペーン中にでもまずは触ってみることをおすすめします。
概要
PayPay

| 運営会社 | PayPay株式会社 |
|---|---|
| ポイント還元率 | 0.5% PayPay STEPを達成すると+0.5%還元 |
| 利用可能カード(支払い) | Visa/Mastercard/PayPayカード(JCB含む) |
| 支払いタイプ | クレジットカード決済/チャージ残高から決済(銀行口座かPayPayカードからチャージ可能)/PayPayクレジット |
| Smart Code | 未対応 |
| 手数料(店側) | 基本1.98%1店舗あたり月額1,980円のPayPayマイストア ライトプランに加入時には1.6%。 |
現状日本で一番使われているQRコード決済サービス。2022年度の国内コード決済のシェアはなんと67%で圧倒的です。
2018年の10月からサービスが開始されています。
支払いは、銀行口座かPayPayカードからチャージをしたチャージ残高(PayPay残高)から支払う方法、クレジットカードと紐づけて支払う方法、PayPayクレジット(翌月銀行口座引き落としかPayPayカード経由のあと払い)があります。
支払った際には利用分の0.5%+αがポイントとして付与されます(PayPayポイント)。
また、お店側のメリットとしてPayPay加盟店では中国の主要QRコード決済であるAliPay+、経由してAlipay、香港のAlipayHK、韓国のKakao Pay、タイのTrueMoney、マレーシアのTouch ‘n Go eWallet、フィリピンのGCash、HelloMoney by AUB、さらに台湾のJKO Pay、PXPay Plus、E.SUN Walletも利用可能にできるのでインバウンド需要も狙えます。
また、PayPayのQRコードを設置すればLINE Payも使えるようになります。
LINE Pay(2025年4月30日にサービス終了予定)

| 運営会社 | LINE株式会社 |
|---|---|
| ポイント還元率 | 0%Visa LINE Payクレジットカード保有者なら最大3%還元 |
| 利用可能カード(支払い) | Visa LINE Pay クレジットカードのみ可 |
| 支払いタイプ | チャージ残高から決済 / Visa LINE Payクレジットカードから決済 |
| Smart Code | 対応 |
| 手数料(店側) | − |
LINE PayはLINEが提供するQRコード決済です。基本的に小規模な店舗よりも大型チェーン店に導入されていることが多いです。ユーザーがQRコードを読み取るタイプでは、LINE Payのコード決済は、PayPay加盟店に申し込むことで利用可能になります(LINE Pay専用のQRコードの表示はなくなりました)。
LINE Payアカウントの残高から支払う形です。
LINEが発行しているVisa LINE Payクレジットカードを紐付けて支払うと、ランク(マイランク)に応じて最大3%のポイントが貯まるというシステムです。銀行口座などでチャージ残高してから支払ってもポイントは貯まりません。
楽天ペイ

| 運営会社 | 楽天株式会社 |
|---|---|
| ポイント還元率 | 支払い方法による楽天カード・楽天銀行デビットカード払い時、ポイント払い時、楽天銀行口座払い時に還元率1%。チャージ払い時には1.5%。 |
| 利用可能カード(支払い) | Visa/Mastercard/JCB/American Express |
| 支払いタイプ | クレジットカード決済 / 楽天銀行口座払い / 楽天キャッシュ / 楽天ポイント |
| Smart Code対応 | 未対応 |
| 手数料(店側) | 3.24%支払元が楽天カード以外のJCBカードの場合、3.74%。 |
楽天ペイは楽天が提供している決済サービスの総称ですが、QRコード決済も提供されています。
支払いは楽天のアカウントに紐付いた、各種カードが利用可能です。楽天銀行の口座払い、楽天キャッシュにチャージした分からの支払いも可能。楽天ポイントから自動的に支払うようにも設定できます。
楽天キャッシュにチャージした分から支払えば、チャージ方法を問わず、還元率は1.5%になります。
しっかりとした加盟店審査があるので、個人間の決済に気軽に利用できませんが、ローソンの他に、楽天ペイの端末を利用している多くの小売店で利用可能です(アプリ上から近くの利用可能なお店を検索できます)。
楽天ポイント払いでもポイントが貯まるので楽天ポイントの消化におすすめです。
d払い

| 運営会社 | NTT docomo |
|---|---|
| ポイント還元率 | 基本的に200円で1ポイント |
| 利用可能カード(支払い) | dカード/Visa/Mastercard/JCB/American Express |
| 支払いタイプ | クレジットカード決済 / チャージ残高から決済 |
| Smart Code | 未対応 |
| 手数料(店側) | 2.6% |
d払いはNTT docomoが提供するQRコード(バーコード)決済サービスです。d払いで支払えば基本200円で1ポイントのdポイントが貯まります。専用のd払いアプリをインストールする必要があります。
支払い時に画面上で利用ポイントを設定して、dポイントを使って支払うことも出来ます。
ちなみにd払いアプリにはdカードのポイントカード機能も付いているので支払いに使わないときでも使えます。
2022年6月1日からdカード以外のクレジットカードで支払った際にはdポイントの付与対象外になっているのでご注意ください。
コード決済だけではなく、d払い残高を非接触決済、iDで使えるd払いタッチなどのサービスも展開しています。
au PAY

| 運営会社 | au |
|---|---|
| ポイント還元率 | 200円で1ポイント |
| 利用可能カード(支払い) | – |
| 支払いタイプ | チャージ残高から決済 |
| Smart Code | 対応 |
| 手数料(店側) | 2.6% |
au PAYアプリから利用できるQRコード決済です。
貯まるポイントはPontaポイント。キャンペーンが多いのが特徴。
通常の還元率は200円で1ポイントで還元率は0.5%。
チャージした残高をau PAY、au PAYプリペイド、au PAYプリペイドを登録したApple Payでも使えます。
メルペイ

| 運営会社 | 株式会社メルペイ(メルカリの子会社) |
|---|---|
| ポイント還元率 | なし |
| 利用可能カード(支払い) | – |
| Smart Code | 対応 |
| 手数料(店側) | 2.6% |
メルペイは2019年3月からQRコード決済のサービスを開始。
メルペイでは、設定したApple PayのiD、おサイフケータイのiDで支払うか、もしくはQRコード決済で支払うという形でメルカリの売上金、チャージ金額を利用できます。

メルペイスマート払いという後払いの仕組みをプッシュしている決済サービスです。
pring

| 運営会社 | pring(メタップス子会社) |
|---|---|
| ポイント還元率 | – |
| 利用可能カード(支払い) | 三井住友銀行、みずほ銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、地方銀行5行 |
| 支払いタイプ | チャージ残高から決済 |
| Smart Code | 対応 |
Googleに買収されたことで一気に存在感を増したサービスです。
個人間送金サービスとして有名ですが、決済サービスとしてもSmart Codeで使えるところで利用可能です。
チャージのための口座には三井住友銀行、みずほ銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、ゆうちょ銀行、地方銀行などが利用可能です。
EPOS Pay

| 運営会社 | 株式会社エポスカード |
|---|---|
| ポイント還元率 | 0.5%- |
| 利用可能カード(支払い) | エポスカード |
| 支払いタイプ | クレジットカード決済 |
| Smart Code | 対応 |
EPOS Payはエポスカードのアプリから起動できる丸井グループのQRコード決済。
2018年8月28日から一般向けに機能が開放されています。
自分で金額を入力して店舗が読み取るタイプのQRコードコード決済。
エポスポイントを支払いに充当することが可能です(エポスポイントを実店舗で使える)。
atone(アトネ)

| 運営会社 | 株式会社ネットプロテクションズ |
|---|---|
| ポイント還元率 | 0.5%(200円につき1ポイント)分のNPポイント |
| 1回当たりの限度額 | 注文金額の合計が50,000円まで |
| 支払いタイプ | 1ヶ月後にコンビニで支払い、もしくは毎月指定日に口座振替で引き落とし |
| Smart Code | 対応 |
atone(QRコード決済)は料金後払いサービスのNP後払いなどを提供するネットプロテクションズが提供するQRコード決済。
2018年10月末からサービス開始。QRコード決済でも後払いという仕組みを採用しています。
導入しているお店でQRコード決済をしたら、1ヶ月後に請求書が届くのでその請求書を持ってコンビニで現金払いをする、もしくは、引き落とし口座を設定してクレジットカードのように口座振替で支払います(毎月27日)。
決済をするたびに200円で1ポイントのNPポイントが貯まり、貯まったポイントは次回の決済に1ポイント=1円で利用可能です(ポイント値引き)。
QUOカードPay

| 運営会社 | 株式会社クオカード |
|---|---|
| ポイント還元率 | なし |
| 利用可能カード(支払い) | – |
| 支払いタイプ | チャージ残高から決済 |
| Smart Code | 未対応 |
ギフトカードとして有名なQUOカードが2019年3月に開始したQRコード決済サービス。
プリペイド式の電子マネーで、残高分のみ利用できます。
残高が足りない分は現金とのみ併用が可能です。
個人で購入して利用するというよりは、贈答品として送られてきて利用する方がメインになるかと思います。
J-Coin Pay

| 運営会社 | 株式会社みずほ銀行 |
|---|---|
| ポイント還元率 | なし |
| 利用可能カード(支払い) | みずほ銀行、三菱UFJ銀行、その他60以上の金融機関 |
| 支払いタイプ | 登録した銀行口座から引き落とし |
| Smart Code | 未対応 |
約60の金融機関(みずほ銀行、三菱UFJ銀行、地方銀行が中心)と連携されています。
ユーザー間での送金も無料で可能。
ことら送金に対応しているので残高を銀行口座に送金可能です。
銀行Pay(GMOペイメントゲートウェイのOEM)
GMOペイメントゲートウェイが提供するQRコード決済サービスを各銀行がOEMという形で提供しています。
メガバンクが提供しているBANK Payとは別物です。
- 横浜銀行が提供するはまPay
- ふくおかフィナンシャルグループ(福岡銀行、熊本銀行、親和銀行)のYOKA!Pay
- 沖縄銀行が提供するOKI Pay
- りそな銀行、埼玉りそな銀行のりそなウォレット
- ゆうちょPay
などがすでに導入済みです。
ファミペイ

| 運営会社 | 株式会社ファミリーマート |
|---|---|
| ポイント還元率 | 200円ごとに1FamiPayボーナス |
| 支払いタイプ | チャージ残高からの支払いレジでチャージ(現金)、クレジットカード(JCBカード(ファミマTカード含む))でチャージ、Apple Payでチャージ。銀行口座からのチャージ |
| Smart Code | 対応 |

決済金額200円につき1ポイントのFamiPayボーナスを得ることができます。
また、クーポンを選択して、ファミペイで支払うことで、決済とクーポン適応が同時に行われます。ポイントカード機能も付帯しており、Tポイント、楽天ポイント、dポイントと連携することで利用者が好きなポイントを貯めることもできます。
チャージ方法はJCBカードからのチャージ、レジでの現金チャージ、銀行口座からのチャージです。貯まったFamiPayボーナスを支払いに充当することもできます。
ファミリーマートでごみ袋や公共料金の支払にも使えます。
バーチャルカードを発行してApple Pay、Google Payで使えるなど、コンビニが提供しているコード決済の枠を飛び越えたサービスになっています。
Bank Pay

| 運営会社 | 日本電子決済推進機構 |
|---|---|
| ポイント還元率 | なし |
| 利用可能カード(支払い) | みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行等最大1,000行が参加予定 |
| 支払いタイプ | 登録した銀行口座から引き落とし |
| Smart Code | 未対応 |
J-Debitを発行している日本電子決済推進機構の提供するQRコード決済です。三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行の3大メガバンクを中心にしたメガバンク連合が参画しています。

QRコードを読み取って金額を入力して決済を完了させるMPM方式のみの提供となっています。
最大1,000行が参加予定とのことです。手数料は1%台(詳細は要問合せ)。
GMOペイメントゲートウェイが提供している銀行Payとは別物ですが、加盟店相互開放などで連携していくかもしれないという発表をしています。
イオンペイ
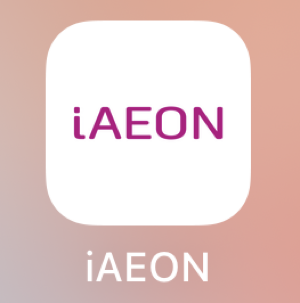
| 運営会社 | イオンスマートテクノロジー株式会社 |
|---|---|
| ポイント還元率 | イオングループではポイント2倍で200円で2ポイント |
| 利用可能カード(支払い) | イオンカード |
| 支払いタイプ | クレジットカード決済 / チャージ残高からの支払い |
| Smart Code | 未対応 |
イオンはiAEONというアプリでイオンペイが使えます。

イオンカードを登録して決済、または、イオンカード、各種銀行口座からチャージをして支払います。イオンカードを持ち歩かなくても決済ができて、かつ、各種キャンペーンなども享受できます。
イオンモール、まいばすけっと、ミニストップなどイオングループで使えます。その他、スーツのAOKI、アート引越センター、ケーズデンキ、ほっかほっか亭などでも導入されています。
MyJCB Pay

| 運営会社 | JCB |
|---|---|
| ポイント還元率 | JCBカード払い時と同様 |
| 利用可能カード(支払い) | JCBオリジナルシリーズ |
| 支払いタイプ | クレジットカード決済 |
| Smart Code | 対応 |
国際ブランド・クレジットカード会社のJCBが提供しているコード決済です。
JCBカードの管理アプリであるMyJCBアプリから設定して利用します。実カードがなくても支払いができるというもの。↓はJCB CARD Wを紐づけています。

JCBは独自のQR決済網としてSmart Codeを展開しているため、そこに自社のQRコード決済も載せた形です。
その他
↑で挙げたファミペイやイオンペイなど、QRコード決済には会社が独自に作ったものもあります。
代表的なのは日本交通グループが提供しているタクシー配車アプリのGOに搭載されているGO Pay。タクシー内でQRコードを読み取れば、登録しておいたクレジットカードから決済ができます。
他にもコーナンが出しているコーナンPay、ユニクロのUNIQLO Pay。その他、鹿児島銀行が提供しているPayどん、などもあります。
以下、チェーン店やサービスが独自に展開しているコード決済の一例です。
独自のQRコード・バーコード決済例
- ファミペイ(ファミリーマート)
- イオンペイ(イオングループ)
- GO Pay(TaxiアプリのGO)
- UNIQLO Pay(ユニクロ)
- にゃんPay(ヤマト運輸)
終了したQRコード決済
- Origami Pay・・・2016年5月に開始、2020年6月に全サービス終了
- pixiv PAY・・・2017年8月10日に開始、2020年12月1日にサービス終了
- Amazon Pay・・・2018年に開始、2022年1月31日に実店舗決済のサービスは終了(オンライン決済は継続)
- ANA PAY・・・タッチ決済に対応して、現在のコード決済は2023年11月にサービス終了。11月以降に新しいコード決済が開始予定。
まとめ
↑のデメリットで挙げた通り、日本国内ではクレジットカード(タッチ決済)、Suicaなどのソニーが開発したFeliCa方式の電子マネーが主流で種類も豊富、決済の選択肢が多岐に渡っています。そこにQRコード決済が加わった形です。
このページの長さをご覧いただければわかる通り、QRコード決済サービスが増えすぎて、店舗ごとに使えるサービスが違うし(店舗側も何を導入したらいいのか正解が見えないし)、Smart Codeなどのおまとめサービスを導入していたとしてもユーザーが何を使ったら良いのかわからなくなりつつある、のが現状かなと・・・。
ただ、そんな中で、街なかのお店で使えるところが多く、利用者が多いため個人間送金としてもよく使われるPayPayの存在感がかなり大きくなっています。
今後、PayPay以外のサービスがどのように展開&対抗していくのでしょうか。